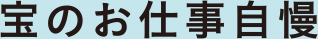#08
之乎路窯(しおじがま)
町の中心にほど近い、宝達志水町子浦。
町家が並ぶ中に、之乎路窯はあります。
二人の人柄に惹かれて、ふらりと立ち寄る人も多いという作業場には
いつでもご夫婦の明るい声が響きます。
この地には、表現したい景色があり、作品を織りなすための素材がある。
私には、続けたい仕事があり、米があり、そして家族がある。
そんなシンプルで豊かな環境を宝としながら
定収はないけどね、と笑うお二人の仕事への姿勢は、
ある意味、とってもイマドキなのかもしれません。
能登の風景を焼き付ける
――陶芸をはじめたきっかけと、作品の特徴を教えてください。
孝之さん:僕は、生まれが石川県志賀町だったので、旧高浜高校(現志賀高校)に通ってたんですが、そこで能登大社焼※の先代が美術の講師をしていらしたんです。その先生から、在学中に、「私のところで2、3年焼き物をやってみるか。学校出てからやるより、今はじめたほうが早いよ」と声をかけられたのがきっかけですね。在学中に焼き物をはじめて、卒業と同時に大社焼に弟子入りしました。そこで16年くらい学んだ後、平成4(1992)年に独立しました。
今は、大社焼きとはちょっと違う雰囲気の焼き物をつくっています。僕の特徴は、釉薬(ゆうやく)を何種類も使って、模様のように表現することかな。筆で絵を描くのではなく、4種類か5種類の釉薬を重ねたりしながら、グラデーションを入れたり、ぼかしを入れたりします。たまに上絵を描いたりもするけど、釉薬のみの作品が中心です。
土は、赤土、黒土、九谷焼で用いられる白土など、いろいろな土を使っています。どれも単品ではなく、ブレンドして使用しています。
※能登大社焼:石川県羽咋市にて、昭和23年に礒見忠司が開窯した窯元。生の葉をそのまま焼き付ける「真葉手(しんようで)」が有名。

向瀬孝之さん
――どんなものをイメージして、作品を作られるんですか?
孝之さん:宝達志水町の風景だったら、海をテーマにすることが多いですね。桜の花びらをモチーフにしたお皿も作っています。
志賀町に暮らしていた頃、親父が定年退職してから伝馬船を一艘買って、趣味で漁をはじめたんです。僕も朝5時に起こされて、網を引き揚げる手伝いをさせられたりしたんですが、朝陽が昇って、それが海面に反射するのがきれいでね。大人になってからも、その景色が懐かしく思い出されて、作品に表現したりしました。夜になるとイカ釣りの漁火が並ぶ光景も覚えてますね。今はLEDになっちゃったけど、昔の電球の黄色が幻想的でよかった。これも作品で表現しましたね。
――自然や風景をテーマにすることが多いんですね。
孝之さん:いろいろやってみていますね。宇宙をテーマにしたこともあったし。犬や猫などの造形もつくるし。作風が多様なので、よく「一人の作品じゃないみたいだ」って言われます。でも、いろいろつくっていると、それぞれ組み合わせたりもできるから楽しいです。
同じテーマを突きつめるっていう場合もあるんですが、そうすると、行き詰まってしまった場合に、ちょっとだけ形を変えるっていうような方向に逃げたりしちゃったりするんですよね。だから、一晩寝かせたり、一旦、別のものをつくってバランスをとったりしながら調整します。意外と、制作の過程で試行錯誤している荒い感じが良くて、最後に均してきれいにしちゃうと、急に力強さがなくなっておもしろくなくなったり。難しいですよね。

能登の海と漁火をイメージした花器
工業製品ではないからこその、おもしろみ
孝之さん:僕の場合は、筆で絵を描くスタイルじゃないので、ある程度の予想はできても、焼き上がりを見るのはいつもドキドキしますね。窯から出した時に「おおっ!」ってつい言っちゃうものもあれば、「あっりゃー…」と頭を抱えるものも(笑)。失敗した釉薬のバケツもいっぱいありますよ。
――「あっりゃー」(笑)。でも、仕上がりがわからないからこその醍醐味があったりしますよね。
孝之さん:そうですね。基本的に、僕らがつくっているものは工業製品じゃないから、似たものはできても同じものはできないし、釜によっても仕上がりが違う。ちょっと歪みがあっても、それが味になったり。おもしろいですよね。
こういう仕事をしていると、作品は残るので、かつて自分がつくった作品に出会ったら恥ずかしいところもあるし、あの時これ良かったなっていうのもあるし、かつてつくった作品から改めてヒントを得たりということも、結構あります。
――作品にご自身のその時が現れているんですよね。制作にはどれくらい時間がかかるんですか?
孝之さん:制作自体は2、3日ですね。考えている時間が一番長いかな。昔、尊敬している先生に、「死ぬほど悩まないとダメだと。辞めてしまいたい、死にたいと思うくらいまで考えろ」って言われたことがありますけどね。
――では、その言葉を胸に、制作を続けられておられると。
孝之さん:いや、今はもう歳とっちゃったから(笑)。以前は作品にかかったら3日とか5日とか徹夜して悩んだりしていたけど、最近は妥協するのが早くなっちゃった(笑)。
――日展※の初入選が1989年。その後もよく、展覧会には出展なさっていらっしゃったんですよね。
孝之さん:そうですね。師匠が日展系の作家だったので、僕も日展系の展覧会に作品を出していました。最近は、僕も審査をする側になりましたけれども。
作品に対する姿勢や苦労は、皆さん同じです。先輩たちから意見を聞いたり、参考にしたり、勉強できる。そんなところに、展覧会に出展する意味があると思っています。意見を聞いた上で、言うことを聞くか聞かないは、本人次第ですからね。僕も「お前は一匹狼だな」とか言われましたよ(笑)。でも、全部言うこと聞いていたら何もできなくなるしね。
展覧会を通じて、人のつながりも増えました。展覧会のパーティを通じて知り合った星稜高校の山下智茂監督から、「(当時教え子だった)松井選手が三冠王を獲得したら、何か焼いてよ」って言われたり。結局、その年に三冠王は獲れなかったんですが、松井選手がニューヨークヤンキースに移籍することになり、門出の祝いとして、花器を焼いて贈りました。
※日展:日本美術展覧会の略称。公募展覧会の一つ。伝統的な技法を守りながらも、現代の生活に適合した新しい造形を追求する作品が多い。

作品づくりのできる環境が、宝
――陶芸をやってなかったら何になっていただろうって考えたことはありますか?
孝之さん:自動車の整備とかかな。機械いじりとかが好きだったんです。中学生の頃は、バイクのエンジンを分解したりするのが好きだった。
――自動車の整備をしていたら、全く違う人生を歩んでいることになりますね。
孝之さん:どっちが良かったのか、わからないですね。自動車の整備だったら定収を得られるし、今よりずっと生活は良いはずだし(笑)。陶芸家って仕事は生活面には安定がないからね。
でも、陶芸はやりがいはあるし、生き方としては面白かったかなと思います。まあ、周りに迷惑かけてるけれど(笑)。
――奥さんは、生まれも育ちも宝達志水町ですか?
真紀さん:私は生まれも育ちも宝達志水町で、学生時代は金沢にいました。金沢にい続けたかったんですが、長女のために宝達志水町に帰ってきました。それからはずっとこの町ですね。
孝之さん:僕は婿養子なんです。結婚の後も仕事は続けても良いっていう条件だったし、向瀬家のご両親がお百姓さんだったから、米だけはある。ともかく最低限、飯は食えるなって思って(笑)。
真紀さん:へえー。そうですか。そんな想いでお婿さんにいらしたんですねえ…。
――そんな想いでいらしたんですね(笑)。でも、ウェブサイトの問い合わせ先は奥さんの「真紀まで」って書いてあったり、今では、持ちつ持たれつの関係なんですよね、きっと。
孝之さん:僕は職人タイプなんで、人の名前を覚えるのが苦手なんですよ。逆に妻は、しっかりしたセールスマンです。
真紀さん:今は携帯電話になっちゃったから全部は覚えれないけど、昔は、関係者の電話番号は、全部覚えてましたよ。もちろん顔もだいたい覚えてます。

ウェブサイトを通じての注文が多い、黒猫の置物
――では、そんなセールスマンの真紀さん。孝之さんの品物は、どこで買えるんでしょう?
真紀さん:ここで買えます(笑)。あとは、金沢市の「ひろた美術」さん、七尾市の「能登食祭市場」、白山市の「ギャラリーノア」、津幡市のギャラリー茶房「甚や倶楽部」などです。最近は、ホームページを見た方から注文をいただくこともあります。実物と写真は見え方が違うときもあるので、そこはご理解いただきたいですね。
結婚式の引出物や記念品などの注文も受けています。申し込みいただければ、陶芸体験もできます。
――なるほど。さすがの明快なご回答、ありがとうございます。では、最後になりますが恒例の質問です。あなたにとっての「宝」、教えてください。
孝之さん:そうですね。自分が思うような作品づくりが出来る環境、ですね。
家族には支えられていることはもちろん、向瀬家が農家だったので、藁灰や籾灰は自分で用意できたし、例えば町内のりんご園の方から、剪定した枝を燃やした灰をもらったりと、天然の釉薬、自然釉の原料が手に入るのは、ここの町の良さですよね。
あとは、自分がつくり出した作品が、お客様に受け入れられて喜んでもらえた時も宝の瞬間ですね。しみじみ、そう感じます。
(取材:安江雪菜 撮影:下家康弘 編集:鶴沢木綿子)